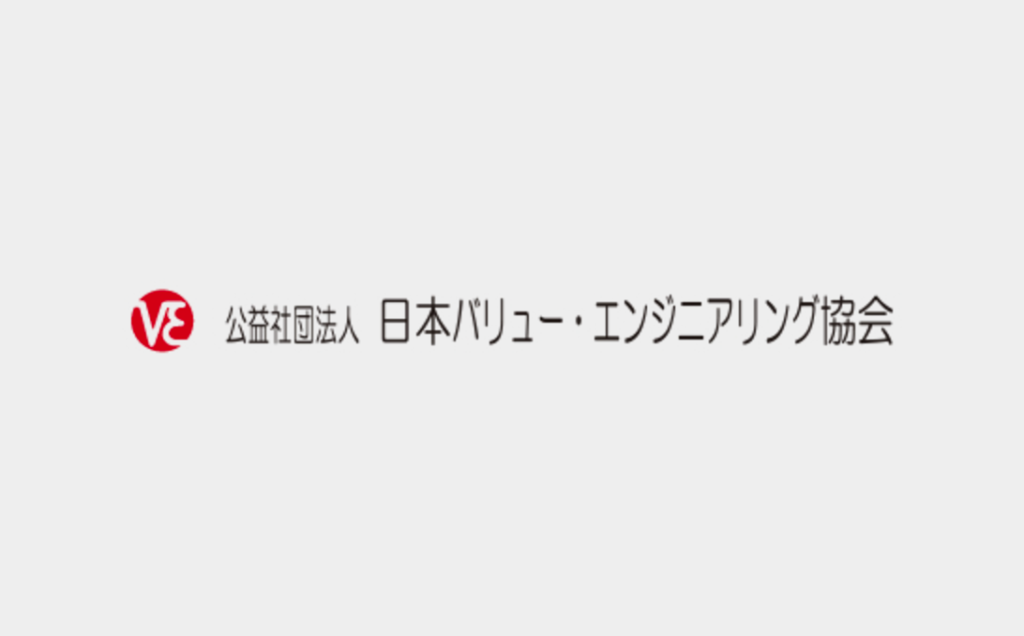-

VEとISOとの相互活用提案
建設業では品質規格ISOの認証取得ラッシュが続いている。当社でも全支店で品質規格ISO9001の認証を取得することができた。一方、当社では30年にわたりVEに取り組んできた。VEとISOとは、どんな関連があるのだろうか。個別に運用していてよいのだろうか。本論文では最初にVEとISOとの関連を分析し、それぞれの性格を明らかにする。その後、企業にとって効率的で効果的な運用をするための提案を行う。標準的 -

設計案評価のためのコストモデル式の作成と活用方法 ==少ない実績データのもとでの概算見積==
設計案を評価するには通常コストテーブルが活用される。コストテーブルの一形態としてコストモデル式を採用する企業が多くなってきた。多くのコストモデル式は統計的手法を用いて作成されているので、それに見合うデータ数が必要不可欠である。しかし、現実には数多くのデータが入手できないことが多く、このときはこの手法は採用できない。われわれが開発した重み付け分析や制約付回帰分析と称する技法によるとこの制限を解消でき -

先導的顧客の機能評価に基づく新製品仕様の評価法 ~インターネットによるコミュニケーション情報の活用~
今日のヒット製品は突然生まれてきては消えていくという浮動的、流動的な特徴をもち、個性的な顧客の潜在的なニーズやウォンツをタイミングよくとらえたものが多い。このようなとらえづらい顧客のニーズやウォンツに俊敏(agile)に対応していくには、新しいものを好む先導的顧客の動向を常時把握していなければならない。彼らは当該製品群に対するオピニオンリーダー、すなわち一般ユーザーに大きな影響を及ぼす先導的顧客だ -

顧客の曖昧な評価額を統合した付加機能の戦略的価格設定
市場における競争優位性を確保するためなどで製品差別化を行うにあたって、重要な役割を果たすのが付加機能である。本研究では、付加機能に対する顧客の曖昧で、しかも、顧客間でバラツキのある評価額を統合して顧客評価額の代表的価格を算出すると共に、この代表的価格の増減に伴う需要量の変化を予測する方法を提案し、この手法を活用してその付加機能の戦略的価格設定や開発設計段階における製造原価目標の設定などが合理的に行 -

資材共同開発VEの一方法論の提案
求められる機能を提供する企業にとって、新しいコンセプトの提案をして潜在ニーズを掘り起こし、そのニーズに沿ったシーズ開発をする必要に迫られている。一方、新しい価値を創造し、明確に他製品を差別化するための鍵を握るのは、製品を構成するキ一部品/キー材料ともいわれていることから、開発企画段階から、製品開発側の発注者と資材供給側の取引先との両者の研究開発部門を参画させたプロジェクトをつくり、両者が共同して製 -

機能のコスト評価に関する考察
取り上げたVE対象の機能評価を行う際に、実用的には機能別にコスト分析したあと、このコストを基準にして、機能評価値をきめ価値指数を求めて判定する。その過程で、多くの場合は全体の低減目標などのバランスだけで、解決のつくものもあるが、扱うシステムが大きくなり、また新しい機能を追加したり、ソフトを対象にするようになると判定が複雑となる。本論文は、機能のコスト評価の段階で、目的にあった評価の価値指数を求める -

機能部品メーカーに有効な攻めと守りの原価企画
企業が永続的に発展するためには、それぞれの製品が必要利益を確保していかねばならない。そのための方策として原価企画が有効である。しかし、従来発表された原価企画は、どちらかというと完成品メーカー(例えば自動車とか、家電製品等)の新製品開発段階における展開方法に関するものが多く、部品メーカー(この場合、機能分野ごとに引合いを受けて生産している専門メーカーをいう)にとって活用しづらいものが多かった。本論文 -

感性機能における機能定義の研究
社会は人間の倫理観と美意識からなる価値観により変化する。企業はこの変化に対応し、価値の高い商品やサービスを市場に提供することで、社会に貢献し、存続をしている。VEでは機能を「使用することを目的とする使用機能」と「色彩や形状などの顧客の欲求を刺激する貴重機能」に大別してきた。近年は顧客の欲求の対象が「物中心」から「人中心」へと大きく変わり、利便性、快適性、嗜好性、安全性などのような「人間の感性に関わ -

オブジェクト指向によるVE展開手法
目的を確実に達成する機能をもつ「オブジェクト」という抽象的概念を取り入れることにより、建築を構成する「商品」・「サービス」を「抽象的な階層化されたツリー状の構造をもつ、オブジェクトの集合体」としてとらえることができる。この集合体の目的を実現する手段としてのオブジェクトをシステム的手法で抽出し、段階的に細分化、詳細化・具体化する。その過程で、その構成品の改善案を順次抽出し再構成する。その再構成された -

使用者機能と基本機能の機能定義に関する一考察
一般的によくいわれることだが、不況時にはコストダウンの管理技術としてVEは重要視され、好況時には忘れられることが多いので、なかなかVEの本質であり、基本である機能定義を正しく理解し、活用している企業は少ないようである。当社においても、VE概念やVE活動は一応定着しているが、VEの基本である機能定義は難解なこともあり敬遠されがちである。本論文は、機能定義の中でも重要であり、その入口でもある使用者機能
VEテクニック– tax –
検索する項目を選択してください。