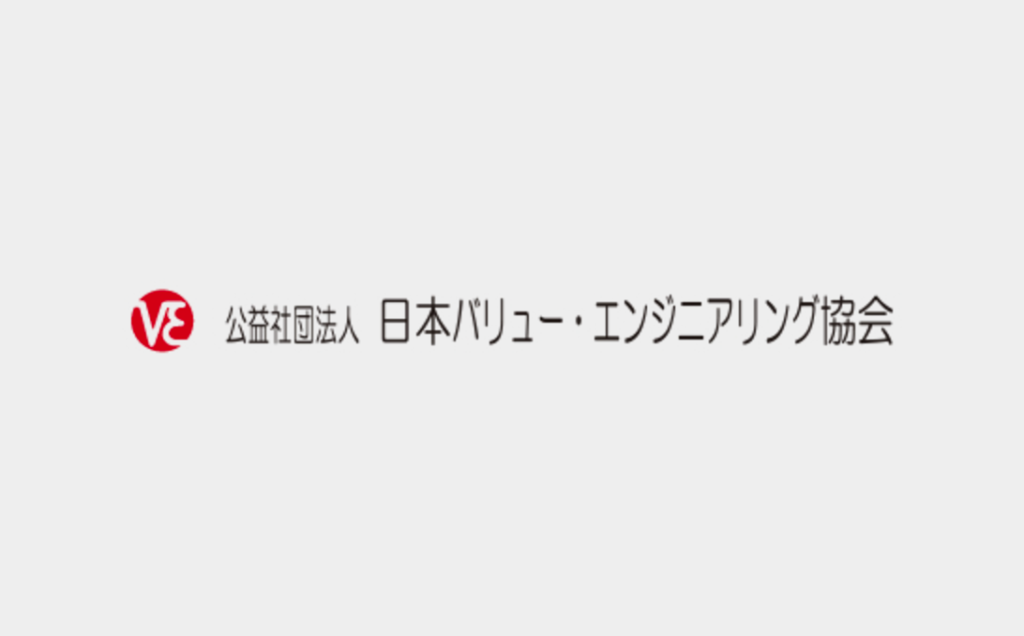-

建設工事における実用的機能分析の考察
企業の存続と発展は,構成職員の"やる気"と"うで"と"健全な組織体"としての自覚を,バランスよく維持向上させているかどうかにかかっている。VEという管理技術は,「うで」を向上させ,その成果に魅入られて「やる気」を出し,結果として「健全な組織体」ができ上るという,時代の寵児ともいえるもので,低成長の分ほど,この持続的な努力の要求される時はないといってよいと思われる。建設業は,VEの特に適した業種と実 -

『商品分析』による材料VEの展開
逆オイルショックに代表される激動の1980年中期を迎えて,世界の経済情勢は,一部の業界を除いて底冷えの状態にある。この零サム時代を生き残るには,世界中の業界をしのぐ強いコスト競走力をつけた企業にならないと,現状設備の稼動を維持できないことはもちろん,利益の維持増加をはかり,次世代の新分野ヘシフトして行くことは困難になってくる。これを乗り切る一つの方策として,固定費増加をもたらさない購入材料を,高効 -

PASS-VE技法
繰り返し行われる改善活動により,各種VE対象の改善余地が低下してきている。改善余地が低下するVE対象から,更に,所定の成果を得るには,機能的な物の見方が有効である。しかし,機能的アプローチを行うVEで,最も重要な機能分析が,上手に,容易に行えない実状にある。これは,日常生活での物の見方,考え方が即物的,具体的であることが多く,機能化,抽象化に慣れないためと考える。不充分な機能分析は,機能にかかわっ -

VEコスト割付技法
VE活動は,利益確保への最も有効な手段の1つとして定着してきている。特に家庭電気製品では,現在,限界普及率に達しているものが多く,生産増による利益拡大は困難な状況にあり,VEに対する期待は,ますます強くなっている。従って,VE予算編成に当っては,他社価格を意識した上で利益を確保する,「かくあらねばならないという予算」となってきているのが現状である。このVE予算を必達するために,VE実務部門は,BT -

制約条件とVE ~制約条件によるVE対象の選定~
建設業が一品生産であり,VEの量産効果があまり期待できない以上,少しでも多くのVE改善テーマに取り組み,改善件数でそれらをカバーしなければならないことは,過去の論文で述べられている。これまで当社の作業所VEは,VE対象選定会議(VE計画会議)によってVE対象の摘出を行っている。従来,ここでとり上げられる対象は,主として顧客の要求する機能や,それらを達成する手段として二次機能を中心に検討されてきた。 -

バリューレイテイング手法 価値の計数化と改善個所の早期発見のための手法
製品のVA活動を実施局面からみると,下流の段階,すなわち2nd Look VAになるに従い,制約条件が多く,実施効果が少なくなる。また,製品のライフサイクルからみると,成熟段階になるにつれて難しさを増す。このため,労力のかかる割には効果が小さい。同じ製品のVAを何回も実施してくると,前の改善個所や問題個所が知り尽くされ,マンネリ化が生ずる。しかし,"改善の余地なし"といった抽象的な判断は,過去のV -

原価低減曲線による戦略的VE目標の設定
VE活動が企業の収益改善に重要な役割を果たしていることは,今更いうまでもない。VEがわが国に導入されて以来,VEの戦術的側面,すなわちVEテクニックは,長足の進歩を遂げ,今後も更に発展することが予想される。しかし,現在のVE活動が,企業の期待する役割を十分に果たしているかとなると,必ずしもそうとはいい難いのが現状である。たとえば,ある不採算製品をとらえてVE活動を実施し,実現化時点では大きな成果が -

サンドイッチ形機能系統図技法
VE活動では,価値の高い代替案を作成することを目的とし,最初に機能分析(機能定義,機能整理,機能評価)を行う。これは,VE対象を的確に把握するためである。中でも機能整理法としての機能系統図の作成は,重要な役割を持っている。しかし,この機能系統図は,時間をかけて作成した割合には,VE活動を通して有効に利用される局面が少ないのが実状である。従って『機能系統図をできるだけ短時間に効率よく作成する』ととも -

一体化思考によるアイデア発想法 --新創造技法の開発--
VE活動において「創造力」は不可欠であるが,持って生れた個人差がつきまとい,訓練や既存の創造技法の助けを借りても,なかなか向上しにくい資質である。また,如何に「知識」が豊富でも,「世の中の汎例や常識の範囲の発想」にとどまる人が意外に多いのに気がつく。「創造力の優劣」は,時には,人の運命を変えたり,また,企業活動においては,製品のライフサイクルや経営数値にも影響を及ぼす。われわれVE担当者にとっても -

『Side Look VE』による生産体質の改善
最も理想とするVE活動の形態は,商品の開発過程に携わるすべての人々がコスト,機能の考え方に立って,仕事を遂行することにあり,改めて計画的にとり入れるべきものではないのが本当だろう。しかしながら,実際のところは,企業内教育として定期的にVErを養成したり,特別なプロジェクトとしてとり上げるほかには,ターゲットが明確になっていないとか,時間的な制約などの理由から,目標が達成できていないなど必ずしも,う
VEテクニック– tax –
検索する項目を選択してください。