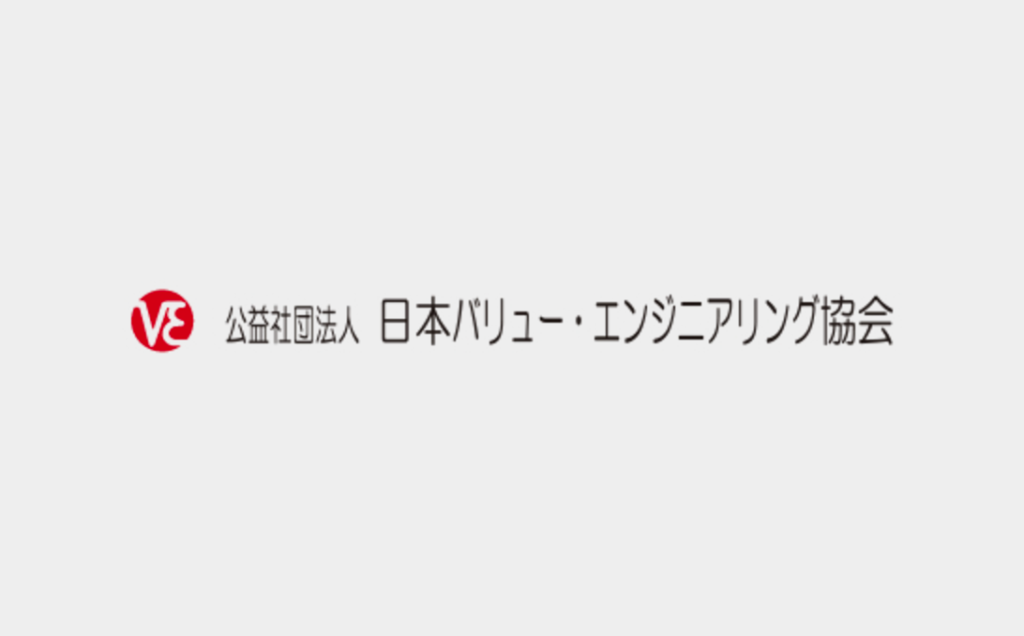-

品質バリューシステムアプローチ
誤差の設計は,設計段階では,いつも後回しにされ,試作後に,対症療法が取られるのが一般的である。その原因は,計算が複雑な上,最近では,部品構成が益々複雑になってきており,一部品の誤差変更が,製品のあらゆる,部位に影響を与えるため,これを一元的に把握して対応するのが,極めて困難なためである。この論文で取り上げるのは,当社における住宅部品の設計に当たり,部品誤差を決定するために開発した手法であり,実際に -

多様化する機能部品選定の1例(機能ポイント法)
ユーザーニーズ,設計アプローチがますます多様化する機能部品を一例に,すべての種類を把握分析し,それらの持っている機能にポイントづけすることにより,コストの順位づけをすることができた。このVE情報を設計部門に提供することによって大きなコストダウン成果を得た。この手法は,機能ごとにコストの重みづけを与えることにより種々の機能部品に適用可能であり,幅広い情報をキャッチできる立場にある資材部門のVE参画の -

VEのためのヒラメキ確保の一手段
人は「あっ,そうか」とか「むっ,あれだな」とか,突然にヒラメクことがある。理屈では割り切れない人脳の特徴である。一般に着想とかヒントは,発想者本人が意識しないだけで,大なり小なり"ヒラメキ"が起点となっている。本論文では,このヒラメキをより効果的に確保するための方法について触れる。具体的には,ヒラメキが大変気まぐれであるという観点から,VE手順とそれを記録に残す態勢の工夫,およびヒラメキ誘発に効果 -

VE活動におけるアイデアの具体化技法(WAMA法)
VEプロジェクトを成功させるうえで,実現性の高いアイデアを沢山出すことは,必要不可欠である。しかし,今までVEの基本ステップの中のアイデア発想において,いかに具体化して行くかという手法については,非常に重要なテーマであるにもかかわらず,あまり基本的な進め方がなく,バリューエンジニアがそれぞれ個人の経験にもとづき推進してきた。今回,効率の良いアイデア発想をするための方法として,フェイズを三段階に分け -

これからのVA提案の評価システム -こうすれば機会損失は減らせる-
最近のVA活動は,益々その適用領域を拡大し,又,活動内容も高度なものになりつつある。この様な活動から創りだされる提案を如何にして効率的かつ効果的に評価し,より大きな成果を引き出すかは当社のみならず多くの企業にとっても共通の課題であると思う。本論文は,当社が運用しているVA提案の評価システムをベースにVA活動における機会損失とは何かを具体的に示し,この損失を最小限に留めるための評価システムを提言する -

VEC計画最適化へのアプローチ -XYZ-VECプランニング法-
企業にとって最大の効果をあげるには経営の最適計画が必要不可欠であり,VEC活動においても同じことが言える。本論文は,受注生産,システムが多岐に亘る,長工期などの特長を有する大型システム製品に対するVEC計画の最適化アプローチ法である。アプローチの方法としては,VEC計画に当り,製品戦略,生産過程における各段階及びVEC活動形態の三つの要素に集約すると共に,各計画要素のメニューを整備して,三つの計画 -

機構部品の最適化設計へのVECアプローチ ~薄板板金部品を例として~
当社のVEC活動は,その対象分野に適した技法を活用し効果をあげてきている。しかし,機構部品へのVECアプローチは,その専門知識にたより,機能追求に欠けていた。従来は,コストターゲットに合わせてアイデア発想,具体化していったが,この方法では,目標がコストしかなく,なかなか新しい切り口が見い出せなかった。本技法では,機構部品の機能から,加工機能展開という新しいアプローチを行い,評価点を算出し更にコスト -

2nd Look-VEC対象品の事前評価法
当工場では製品開発段階からのVEC活動である0 Look,1st Look-VECを重点的に実行し,大きな効果を上げている。しかしながら,一方では収益率の低い製品の収益改善策として2nd Look-VECのニーズも高いのが現状である。一般に,2nd Look-VECは低減ポテンシャルは小さいが,真に有効な2nd Look-VECについては,これを実行する必要があるので,VECの事前に概略の投資効果 -

建築設備業の施工準備段階における『Compact VE』
建築設備業におけるVEテーマの多くは,工事受命後の施工準備段階で抽出される。工事の原案(設計図)の中には利益を生む"宝の山"が沢山ある。また着工後の顧客からの要求事項が追加・拡大されるのも通常のこととなっている。限られた予算の中で顧客ニーズに応え,請負者として利益を確保するために,VEは有効な手段となりつつある。しかし,VEを実行すべき施工担当者は,受命後の業務繁忙の中では十分なVE活動ができない -

VE目標設定のための機能達成度と価格の研究
カラーテレビは,1インチ-1万円と言われた時代があり,製品の価格は,画面の大きさにほぼ比例するとされていた。また家庭用の冷凍冷蔵庫の価格は,庫内容積とほぼ比例関係にある。これに対しマイコン保温釜では,炊飯能力1リットルと1.5リットルの価格差は,僅か5%である。規模の戦略および機能戦略のいずれの展開においても基本機能の機能達成度の水準を変更する場合には,変更後の基本機能のあるべき売価または原価をで
VEテクニック– tax –
検索する項目を選択してください。