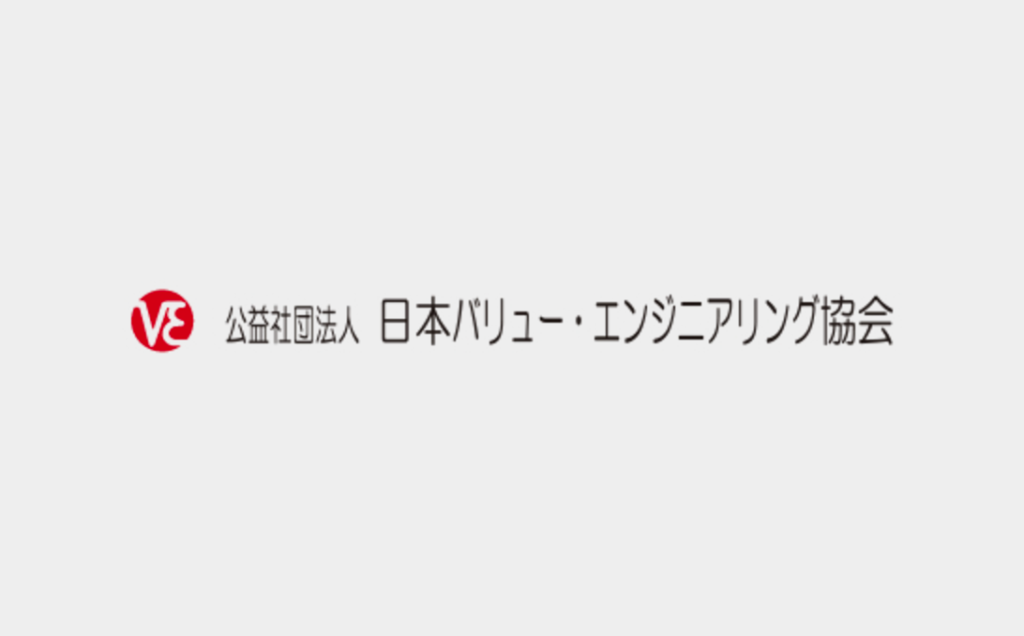-

コンパクトカメラにおける価値評価手法の確立と事業活動への応用
物が溢れる今日、消費者から見れば同じような商品が数多くのメーカーから世の中に送り出されている。これらはメーカ一間の技術力が均衡し、商品そのものの基本機能にも大差がないために、消費者から見るとどれも特徴をつかめず、同じような商品にうつってしまう。このような状況下において、メーカーとしてはどこに顧客の満足度をみいだし、いかにしてヒット商品を作り出すかが、重要な課題となる。本研究では、このテーマに対して -

顧客の機能評価に基づく製造原価目標の構造別細分化とその活用
本研究は既存技術で既存市場へ参入する成熟期にある新製品で、製品差別化に使用・便宜上の機能が主要な役割を果たす製品を対象に取り上げ、製品コンセプトづくりの段階で、顧客の機能評価に基づいて製造原価目標を主要な構造物に細分化する方法を提案するものである。このような顧客の機能評価に基づく製造原価目標の細分化法は渇望されて久しいが、この分野の研究は極めて少ない。そこで、本研究はこの課題に取り組みコンジョイン -

バリエーション群に対する新しいVEプロセスの構築
自動車を構成する部品の中で小物と考えられるような部品は、車両開発日程の後半になって仕様決定されることが多く、これに起因して相手部品(=大物部品等)とのレイアウト上の制約、および派生車型(車種)の追加設定に伴う要求性能の追加等で、部品の種類が多くなるという傾向がある。部品メーカーとしては、これらの製品に対しVEおよび共通化という製品改善を行うわけであるが、前記した傾向が弊害となり、なかなか効果が上が -

建築工事VEにおけるアイデア関連付け法
建設工事の合理化の中で、工法の改革による合理的施工方法の改善が要求されている。建設工事は複数の工事要素の組み合わせにより構成されており、それぞれの要素が密接に関連付けられている。一般のVE手法では、要素別に検討を行った方が具体的なアイデアがでやすいが、その反面、相互関連的な面において支障が出ることも多い。個々の要素では、有効なアイデアでも、前後の関連を見ると有効性が減じられる場合や、実際には採用で -

付加機能に対する顧客評価額の算出法
ヒット製品を作り出すためには基本機能もさることながらその製品の付加機能が極めて重要な役割を果たす。本研究はこの付加機能の評価問題に焦点を当て、その新しい評価方法を提案するものである。本研究では付加機能のうち「顧客が求めている付加機能」を評価対象とする。「顧客が求めている付加機能」の評価値は当然のことながら顧客の評価値に基づくべきであるが、顧客の評価値はそのニーズや、付加機能に対する知識の程度などに -

仕様設定のための価値評価の方法
カーメーカーは車両の商品性向上のために、様々な装備品を開発しユーザーに提供している。それぞれの装備品は標準装着、オプション、車両グレードによる使い分け、等に分類され車両全体の製品仕様に組み込まれる。ユーザーの各装備品に対する評価を正確に把握しユーザーにとって最適の製品仕様を設定できる方法が確立できれば、製品の価値を高める有効な手段となる。従来、製品仕様は様々な情報をもとに経験的な判断により決定され -

機能の重要度による評価に関する一考察 ~「成果で評価する」評価技法のすすめ~
VEの「機能評価」では「機能」が果たす値打ちを、コスト換算(仮に「C」)して、おなじ機能をもつ代替のものや、こと、あるいは理論値で評価(「F」)し、判断材料にする。現状を、改善、改良、組織なら改革する目的で、活動しているにもかかわらず、価値を検討する段階では、例えば、手続きやサービスが対象なら、評価値を強制的に低い数値で割つけ、力を入れたい分野は配分を増やす。また、製品や、製造など、ハードのVE対 -

問題解決のための『入出力形態法』の提起
近年、問題解決のためのシステム化指向が高まっており、情報の概念化と標準化がより一層、求められるようになってきた。本論文で提起する『入出力形態法』とは、問題解決に際しての情報の流れを、簡明な入出力の形態、すなわち入力部、処理部、出力部の三区分に体系化することにより、早く的確に解決法を見い出そうとするものである。意図的に構成フォーマットを同じにし、多くの人が手軽に、かつ一定レベルの情報を確保する狙いも -

VE活動に役立つDFMAによる生産性評価
現在、企画,構想から設計までの開発初期段階のVE活動によるQ.C.D.の作り込みが重要且つ、効果的であると一般に言われている。そして、このことは実際の開発業務におけるVE活動で、数多くの実績を残していることからも証明されている。また、生産部門のフロントローディング化により、開発部門と生産部門の連携によるサイマルテニアス・エンジニアリング活動がクローズアップされている。しかし、現状では、この活動にお -

半導体製造における横断的コスト評価の一手法
半導体に使われる加工用材料のコストを算出し評価しようとする場合(通常ウェーハ当たりで求める)、生産工程が数百ステップもある同一生産ラインでも非常に多種の製品を作っているので原価計算が複雑であった。更に生産ラインが多拠点に分かれている場合、同一製品と言えどもライン間のバラツキによる"ロス"の発生が生じる。本稿の狙いは、同一製品で、加工用材料コストの評価をする場合に、加工の大きな単位である"マスク・パ
VEテクニック– tax –
検索する項目を選択してください。