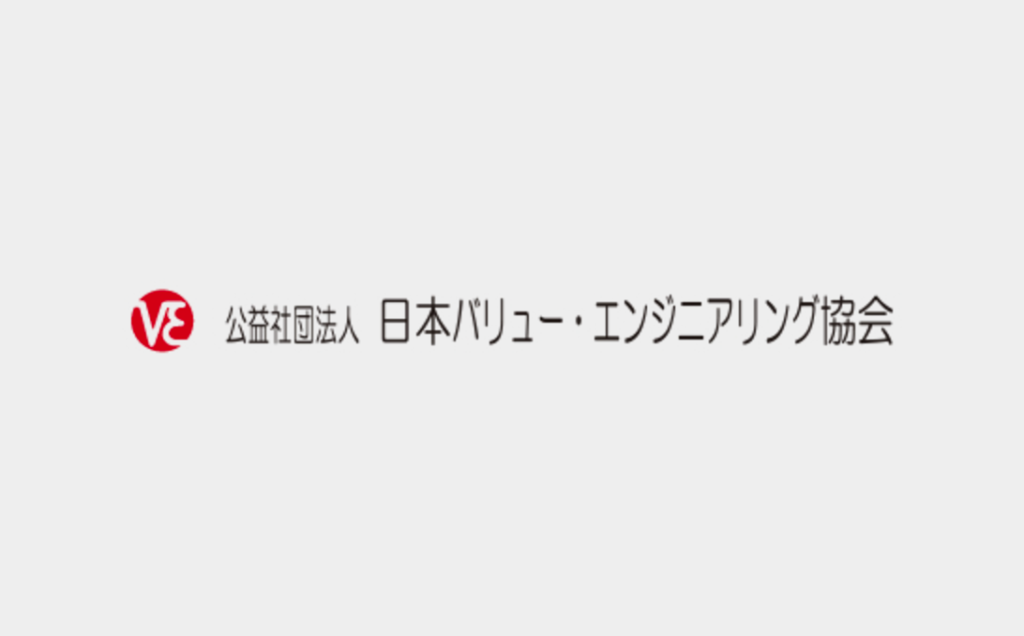-

トータルVE戦略
今日の社会,経済情勢は,企業経営にとって非常に厳しいものがある。とりわけ,高度経済成長と,それに伴う建設投資の緩慢ない伸びが,企業経営にとって不可欠ともいえる建設業界は,かつてない試練の時代に突入している。このような情勢の変化は,企業努力の必要性と重要性を,ますます高めることになった。さらに,このことは,VE活動においても,何らかの転換を計るべき時期であることを意味している。当社では,過去に大会論 -

全社的VEの展開 ~新局面に対応する企業体質づくりの一環として~
実態となった新局面49年のオイルショック後の今日の企業環境を,ややもすると,それ以前の高度成長型時期を尺度にして異常であると思いがちである。しかし,もはやこのような考えでは,現状に対処できないばかりか,環境変化の本流を見い出すことができず,今後の事業運営の方向性を危惧せざるを得ない。従って今日の局面を今後とも,これが常態であると認識し対応する企業体質づくりを,一刻でも早く着手する必要があるといえる -

低成長下の企業経営におけるVA戦略アプ口ーチ(1) 製品企画におけるシステムVAの一考察
1960年代の高度成長期から1970年後半の成長期に移って,わが国企業の多くは攻めの経営から守りの経営へ転換し,その戦略も新製品開発主力製品のシェア拡大からコスト低減へと変ってきている。このような,中で新製品の開発は企業にとって大きな問題となり,NO RISK的,防禦的となってきており,その新製品開発方針も技術革新型から市場革新・拡大型を重視するようになっている。企業の製品をそのライフ・サイクルに -

ステップリスト・マネジメントの方法 ~確実で創造的な管理をするためのツール~
ステップリスト・マネジメントの方法とは「ステップリスト」という書式を道具として使って,マネジメントをする方法につけた名称です。ステップリストの書式とは,第1図に示す通りです。この書式は,こみ入ったマネジメントをするときに,非常に便利なものであり,他にも,考えをまとめたり,新しいことを創造したり,問題を解決したりするときにも,便利に使うことのできる道具です。一般に,ある目的を達するためには,いくつか -

VE活動と経営情報総合管理システム
低成長時代のコンシューマーの眼は,高度成長時代には想像もつかなかった程,厳しくなり,それはあたかも,VE技術者の眼のごとき様相を呈してきた。消費者団体の各方面での活動は,それらを代表するものであり,適正価格の追求,信頼性表示の要求,そして「約束された機能」の判定等,企業に対する要求は,激動する経済環境を反映してか,かなり多様なものになってきている。そうした市場環境に対応すベく,企業のVE技術者に対 -

『ワースト指数』を中心としたVE活動の展開
もはや高度成長経済は過去の甘美な夢と化した。低成長経済を大前提として,企業活動の健全な発展を期して行かねばならい現在,この点での努力と成果が,企業間格差を大きく広げて行くであろうことは,容易に想像がつく。当然,VEに対する要請も過酷なものとなり,より効果の上る手法の登場が期待されている。当事業部においては,昭和48年頃より本格的なVE活動の実用化段階に入り,第1図に示すように着実な成果をあげて来た -

トータルVE VEマネジメントとテクニック
昨年末よりはじまった石油パニック,それに続くインフレ,大幅な人件費上昇と,企業は省資源,省力,省エネルギーといったコストダウンに追われているといっても過言ではない。また社会から,この事を,これ程まで強く要請された事も今だかって無かったといえる。社会の体質が変る時に,企業の体質が,それについて改善されないとしたら,その企業は生き残る事は困難といえよう。一方,かねてからVEにおいては機能の追求を行ない -

量産工場におけるトータルVAプロジェクト組織とその運営
現在,日本経済をとりまく周国の情勢は,激しい変化の様相を,更に,こくしてきております。昨年に始まった,石油パニックと,西欧,米国に進行してきたインフレーションが,更に世界的なインフレーションとして押しよせ,日本が国際社会の中で貿易立国として存在することが,国内コストプッシュ要因の増大に伴なって,大幅に圧縮されつつあり,このままゆけば3~4年間で日本は,完全に国際競争力を喪失する危機に直面してきた, -

企業の体質改善をするシステマティックなVEの展開
昨年わが国に石油パニックを起し,大きなショックを与えたいろいろな問題はまだ記憶に生々しいが,石油に端を発した諸問題は石油のみにとどまらず,我々に資源,エネルギー不足を再認識させる一方,「狂乱物価」と言う流行語までつくり出させてしまった。かって例をみなかった大幅なコストアップ攻勢に対し今後各企業が,この「狂乱物価」をどう吸収対策し,いかにして各商品の付加価値を高めるか,又新しい社会の経済変化に,いか -

経営組織効率化のために果すべきVEの役割
かって60年代においては,わが国企業は経済の高度成長の中にあって,ややもすれば売上高の増大,シェアーの拡大などにより,利益の確保と賃上げの吸収を図ってきたが,今後は経済成長が鈍化する中で,賃上げの吸収と利益の確保を実現してゆかなければならなくなった。さらに,わが国は原材料,燃料等の量的な問題から諸資源・諸エネルギーを含めた,知識集約産業型への構造転換に迫られている。したがって,従来の高度成長に慣れ
マネジメントとVE– tax –
検索する項目を選択してください。