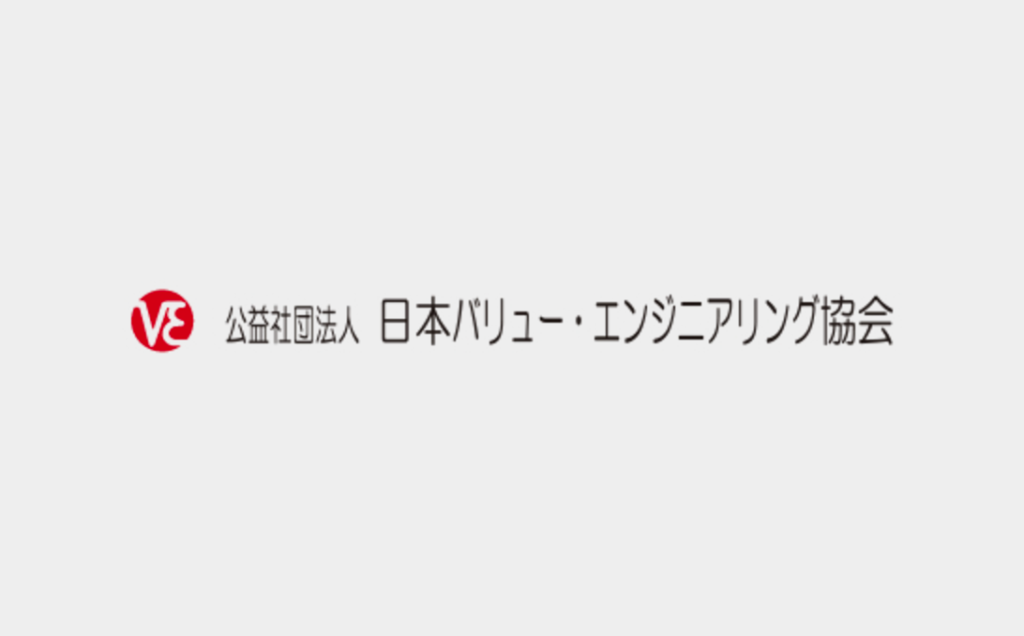-

仕入先からのVE提案に対する報奨制度のあり方について
VEは,日本に紹介されて以来,多くの研究と絶え間ない実践活動の結果,大きく成長し,発展を続けてきました。ところが,VE自体の理論及び実践面での進展に相反し,創始者マイルズ氏の主張された「業者の知識を有効に活用し,その努力に報いる」という,いわゆる報奨制度に関しては,充分な研究がなされてきたとは,いえないのではないだろうかと考えるのであります。当社では,VA(量産段階の価値分析)からVE(設計・試作 -

KJ法を適用した取引先VE教育
現下の厳しい経済体制下において,外注企業は親企業の指導育成に過渡に依存しているだけでは,変化の激しい経済・社会状勢にフォローして行けない。外注企業においても,経営管理に関する手法,例えば,VE,IE,QC,その他ORなど,マスターすることに努力し,利益を自ら計らねばならず,また他面,発注企業としても経営上不充分な点があれば,外注企業を指導して行く必要があると考える。発注企業は,現在取引中の外注企業 -

当社におけるVE展開上の問題点について
現在の電気業界における競争は,熾烈をきわめ,新技術の開発,コスト開発の優劣は,そのまま製品の販売に大きく影響を与えております。このような厳しい市場をはいけいに,コストダウンの手法として紹介されたVEは,各社こぞって導入したことは当然であります。当社においても,このような状勢のもとに,昭和38年,購買部門にて,購入する部品のコストダウンを計ることを目的として,VEを導入し,その任としてVE事務局を, -

VE推進マニュアルとその背景 ~動機づけを中心に~
株式会社日本製鋼所においては,広島製作所が昭和42年11月VEを導入,半年後,室蘭,東京,横浜の各製作所も導入し,全社的なVE活動が展開されようとしている。中でも広島製作所では,VE推進満3ヵ年を迎え,7回に及ぶセミナーと,ON THE JOB TRAINING 方式により,養成されたバリューエンジニアの総数は,230余名に達し,春秋2回実施されるセミナーの期間を除き,年間,常時,6人編成のチーム -

企業内におけるVEの問題点
最近は,VEあるいは価値分析に対する反応が非常に多い。「価値」という問題に,非常に関心がもたれ,バリューエンジニアという専門家が養成されつつある。企業内におけるVEは,アレンジされた形で推進され,定着発展しているが,もう一度,本来のVE理論を基本よりふり返り,再確認し,現在の企業内におけるVEの問題と対策及び今後の方向づけの指針の設定をしてみたい。しかるに1) VEの適用局面2) チームと組織化3
12