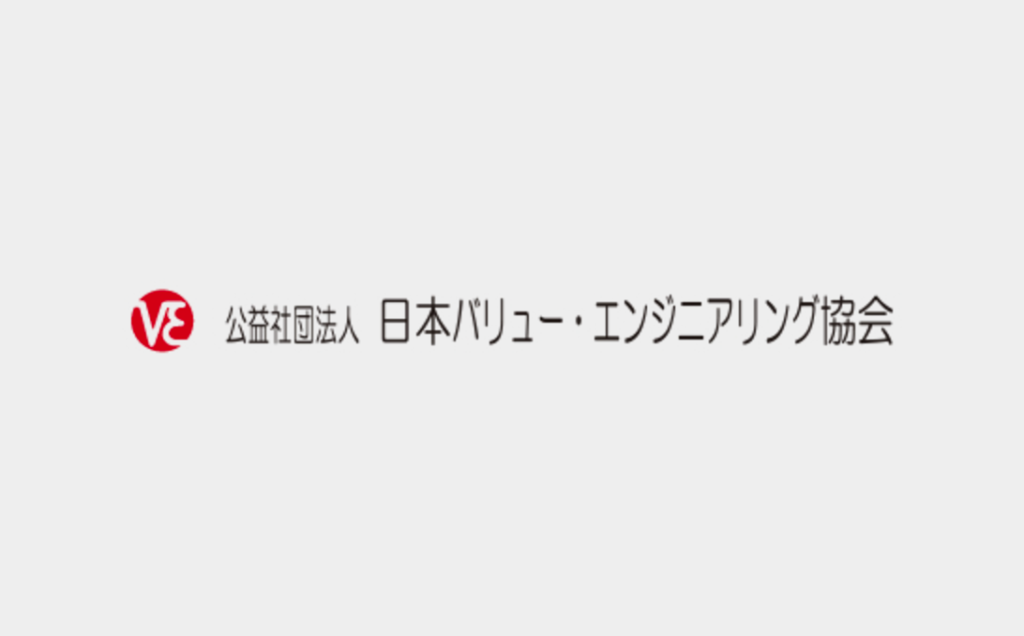-

ソフト機能の評価によるコンセプト・エンジニアリング
今日、顧客の価値観やライフスタイルの多様化、個性化が進み、顧客動向を把握することが非常に困難となってきている。さらに、製品のライフサイクルの短縮化にともなって、「ヒット製品」や「売れる製品」が生まれにくい状況となってきている。このような状況において「売れる製品」を生み出すためには、顧客の欲求を満たす製品を作る方法論が重要である。この方法論が、製品企画段階における合理的な製品コンセプトづくりの方法、 -

建築作業所における施工計画の立案に関するVEの一考察
建設業は個別受注産業で、その都度異なる要求の建物を、その都度異なる生産場所で、厳しい自然条件に対応しながら、主として屋外で生産している。そして、それらの建築物は、施工計画によって品質・工期・安全などが保証される性格を持っている。そのため、施工計画は、設計図書や契約書に示される発注者の要求条件と、生産場所の客観的与条件に基づいて、施工管理をする作業所の担当者と、企業の専門スタッフが英知を結集して、チ -

建築作業所におけるVE活動の効率的な進め方
当社がVEを導入して以来、その活動の中心となってきたのは工事部門のVE活動である。本論文では、その中で、建築作業所におけるVE活動を3段階に分類し、各々の段階ごとの分析を行い、VE活動の拡大を目的とする「量の拡大」と、内容の充実を追求する「質の向上」との両面から効率的なVE活動を推進していくための方策を探ろうとするものである。 -

民間建設工事へのVE条項の適用とその問題点 -社会浸透をめざす建設VE-
VEの有効性が社会的に認知され、建設工事においては請負契約にVE条項を折り込む動きが見えはじめた。本論文では、民間の建設工事契約にVE条項を適用するにあたってのポイントを抽出し、変更提案の際のトラブル等を防止してVE条項を効果的に活用するための検討を加えた。VE条項の民間工事への適用に際しては、受注者は発注者から信頼を得ることを基本に考えて、VEへの理解、契約条項への理解を得るとともに、発注者のニ -

環境保全を志向するVE
かつて生活水準向上と経済力拡大のために進めてきた大量生産、大量販売が環境に影響を与えるようになった。VErが携わって開発した高機能、低価格、高価値製品は顧客の満足を得て、生活の向上と企業の発展をもたらしたが、プラス面だけを評価できない時代になった。これからは企業の環境への取り組みが自らの存在と活動の必須の要件といえる。地球環境問題のような複雑で難しい問題こそVE適用の新分野だと考え、企業市民として -

中小自動車部品メーカーにおけるVE上流化への対応
開発の初期段階にVEを適用することの重要性については言を待たないが、二次メーカ一、三次メーカーと縦の繋がりによって構成されている我が国の自動車製造業界においては、中小の部品メーカーがVEを展開する上で、数々の障害があることも事実である。今回はいすゞ自動車グループ21社が3年に渡って研究してきた『自動車部品を扱う中小メーカーにとって、効率の良いVE展開手法とは何か』についてその研究成果を報告する。 -

建設VEと環境貢献評価
最近特に地球規模の環境問題がクローズアップされ,全世界的に対策の必要性が緊急課題として取り上げられるようになってきた。このような中で,建設産業にとっても環境問題を抜きにしては工事が出来なくなりつつあり,社内における建設VEの中にも環境問題を取り上げたものが多く提案されるようになってきた。そのため,このような環境改善のVE提案を正しく評価するための評価基準が必要とされるようになった。また,環境対策を -

作業所VEの実施方法への一考察
作業所VEに関する手法や実施方法については、これまでに、多くの場で発表され、定着してきた。しかし、最近の社会環境の変化により、ゼネコン各社共、工事量が大幅に増大し、人手不足が叫ばれている。このためVE活動をいかに効率化し、顧客の満足する製品を提供するかを検討しなければならない。本論文では、従来の作業所VEの進め方を見直して現在の企業環境に合わせた、効率的なVEの実施方法、ならびにVEジョブプランを -

建築工事管理の改善活動におけるVE適用
建設作業所における生産活動において、生産性向上の要求の中で生産活動を管理する技術者は減る傾向にあり、工事管理支援システム開発による合理化が必要とされる。そのシステム開発についてVE手法に基づく効率的な方法の開発を試みた。すなわち改善の対象として管理支援システム構築とその運用とに区分し、その取り組みの仕組みが異なるため、対応する内容を明らかにした。また作業所における必要なニーズを的確に確認し、シーズ -

製造VEの一考察
生産性向上は企業における永遠のテーマともいえる。その生産性の向上を製造VEの立場から挑戦してみようと思う。すなわち造り易さの観点からVEを行ない,生産性の向上をはかろうというものである。作り易さの基本は(1)部品を知る (2)工程を知る (3)加工しやすさ,組立やすさを評価する (4)付加価値を生まぬ作業を排除することにあると考え,各々を有機的に結びつけ,それから改善のポテンシャルを導き出し,生産
VEの適用局面– tax –
検索する項目を選択してください。