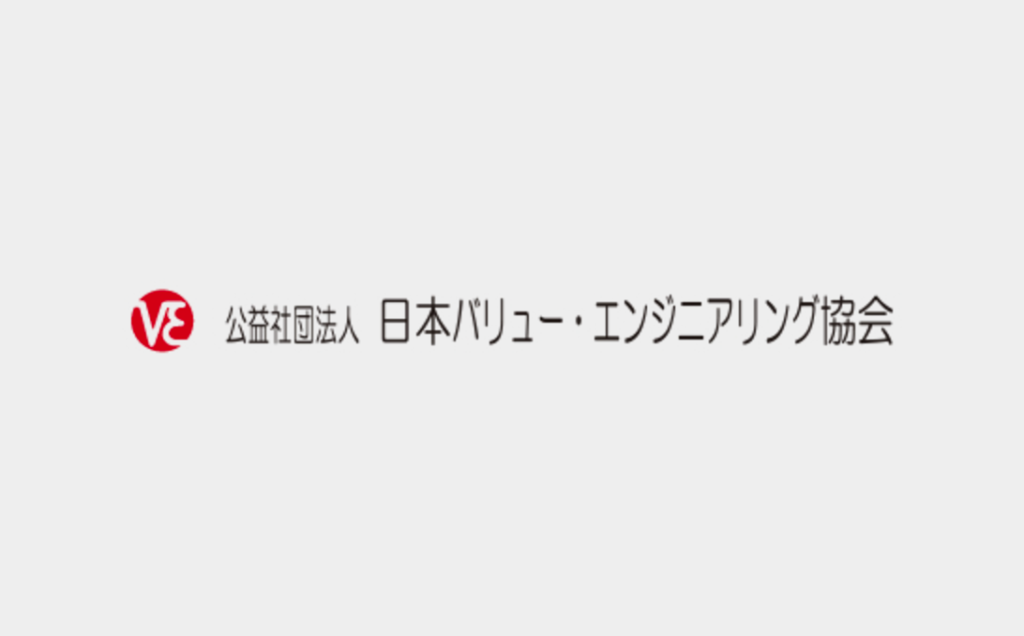-

原子力設備機器に関する材料調達仕様標準化のためのVE活用
原子力発電所は商用運転が開始されてから20年以上が経過し、国内の発電電力量の3割以上を供給しており成長・成熟段階と推定される。原子力発電所の原子力設備を構成する機器(以下機器と称す)は、それぞれ異なる要求機能と使用環境が多く、個別に設計・材料調達・機能向上努力がなされる場合が多い。このため、共通的な材質の機器の素材材料(以下材料と称す)も個別最適化が進み詳細仕様レベルで相違した材料が増加し、調達コ -

公共事業の全実施プロセスにおけるVE活用策の一提案
昨今、年間市場規模50兆円と言われている公共事業は改革が求められ、顕著な改善効果がなかなか本質的に現れてこない。本研究は公共事業のプロセスに焦点を当て、それぞれの段階の課題を抽出する。これらの課題の中、特に発注者側が企画を練る段階に対し、管理技術VEを適宜に応用できる手法を提案することが主目的である。また、全実施プロセスに対しても分析を行い、公共事業の全体へのVE活用の課題提起も行う。 -

行政と住民が協働して市町村・都市計画マスタープラン~地区プラン策定・実施・フォローアップ活動にVEを適用する一考察
この論文は、地域住民が主体となって、便利で、快適で、人情味あふれる個性ある街づくりを実現するために、VEを適用し行政と住民が協働して、街づくりプランを合理的に策定する提案である。従来の我が国の都市計画は行政主導型で、その内容や手続き等は法律で細かく規定され全国画一的であった。これを欧米方式に改め、個々の市町村が各々の特徴や個性を活かし、行政と住民が協働して、『コラボレーション・デザイン』の考え方を -

建設VE検討におけるテーマしぼりこみ法(その2)
建築工事においてVE検討は原価低減のために計画、設計、見積、調達、施工の各ステップにわたり日常的に行われている。特に近年は顧客の機能・コストについての要求が厳しく、効果的なVE手法が求められていた。一方、建築物は構成部品が非常に多く、建築物全体を大きく捉えてVE検討対象を効率的に絞り込むことが難しかった。今回考案した手法は、短時間で建物全体を大きく捉えて価値の高い代替案を提案することを目指した。な -

建設コンサルタント業におけるVE活用策の一提案
本研究は現在国内公共事業の計画、設計を担当している建設コンサルタントが直面している課題を摘出し、今の状況下に活路を見出し、価値向上を図るため、VEを業務上に活用する方法について提案することが主目的である。今回は主に建設コンサルタント業に自主的にVEを行う場合の実行策を提案し、今までVEを実施していない地域計画分野と道路計画分野を例にVEの活用策について詳述する。 -

建設産業における総合技術監理の必要性とVEの果たす役割
建設技術業務の総合化、複雑化などの進展に伴い、業務全般を見渡した俯瞰的な把握・分析に基づき、技術の改善や、より合理的なプロセスによる安全性の確保・外部環境負荷の低減などを実施する管理技術が必要となってきている。これらの管理技術は、それぞれの要求事項を個別に管理していくことのみで実現することは困難で、あり、複数の要求事項を総合的な判断により管理していく技術が必要である。総合的な判断の根底となる管理技 -

建設におけるVEの活用形態とその特徴
建設のVEは、過去に様々な展開の仕方が発表されている。それらは建設の特殊性を踏まえつつ、建設物のライフ・サイクルにおける一局面を取り上げて研究したものがほとんどであった。しかし、社会環境の変化と21世紀に向けて、建設のVEをどのように受け止め、適用していくべきか、再度考えておかなければならない。本論文では、建設物のライフ・サイクルにおいてVEをどのように考え、適用すべきか、その実施形態と特徴を述べ -

土木設計VEを国内の公共事業に定着させる手法の一提案
本論文は建設省が3年間で直轄事業において、土木設計VEを試行してきた状況を踏まえ、その間で証明された土木設計VEの有効性を生かし、早く定着させる方法を提案することが狙いである。その結論として、筆者は3年間の国内経験で、日本の風土と土木伝統に満足させたほうが最も有効であると考える。そこで、官主導型のVEも含めて提案し、移行期間として、建設コンサルタントを始めとする民間はどんな形で協力していくかについ -

建設VE活動の再構築法
当社が約25年ほど前に先行同業他社に学びながら、1st Look VEの実施を試みてVEを導入し、所期の目標をクリアーした普及期を経て、日常業務にVE活動を移行したところ、活動が潜在化・マンネリ化し、更に景気の影響を受けて混乱してしまった要因の分析をおこなった。その打開のため、VEリーダー養成講座を切り口とした、VE基盤再整備と再構築のためのアプローチ方法を提案するとともに、建設業における具体策を -

改正された建築基準法の性能規定化に伴う建設VEの取り組み方
建物を建設する場合、設計・施工の技術基準となるのが昭和25年に制定された法律第201号の建築基準法であり、戦後50年間続いてきた。この建築基準法は「仕様規定型」のため、建設にVEを適用する場合に大きな制約条件となっていたが、今回、基準法の一部が規制の目的や技術水準のみを規定した「性能規定型」に改正(2000年6月に施行)されたためVE効果が期待されている。(以下改正基準法と呼ぶ)本論文では改正基準
VEの適用局面– tax –
検索する項目を選択してください。